📊 この銘柄分析は、AIによる自動分析と公開評価基準に基づいて作成しています。
➡️ AIの銘柄評価基準はこちら
🤖 使用AIの情報はこちら
企業紹介
大末建設株式会社(証券コード:1814)は、大阪市に本社を置く東証プライム上場の総合建設会社です。特にマンション建設において豊富な実績を持つ企業として知られています。
AI銘柄分析レポート
はじめに
本レポートでは、大末建設(1814)の事業内容、財務状況、株価指標、そして今後の成長性について、公開情報を基に客観的に分析し、投資判断の参考となる情報を提供します。
収益性の評価
直近の業績は好調に推移しており、特に経常利益は大幅な増益を達成しました。建設事業において安定した収益基盤を構築していると評価できます。
過去5年間の業績推移
| 決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) |
| 2021年3月期 | 56,490 | 2,214 | 2,219 | 1,603 |
| 2022年3月期 | 69,645 | 2,708 | 2,712 | 1,816 |
| 2023年3月期 | 71,834 | 1,887 | 1,939 | 1,321 |
| 2024年3月期 | 77,815 | 1,590 | 1,602 | 1,235 |
| 2025年3月期 | 89,027 | 3,695 | 3,710 | 2,060 |
| 2026年3月期(予想) | 96,400 | 3,520 | 3,350 | 2,250 |
成長性の評価
2024年度からの中長期経営計画では、事業基盤の変革と成長を目指す方針が示されています。しかし、その目標達成に向けた具体的な戦略や施策の詳細が不足しており、将来の成長性を確実なものとして評価することは困難です。
財務健全性の評価
収益性、安全性ともに概ね良好な財務状況を維持していると判断できます。自己資本比率や流動比率などの主要な財務指標は、安定した事業運営を支えるレベルにあると言えるでしょう。
割安性・株価水準の評価
現在の株価水準は、PERが約11.62倍、PBRが0.84倍となっており、PBRが1倍を下回ることから、理論上は割安と判断できる可能性があります。ただし、これは市場全体の動向や今後の業績見通しによって変動するため、他の要因と合わせて総合的に判断する必要があります。
事業リスクと対応策
建設資材価格の高騰は、同社の収益を圧迫する主要なリスク要因の一つです。また、景気変動の影響を受けやすい業界であるため、不況時には業績が低迷する可能性があります。災害発生時の事業継続計画(BCP)の策定など、リスク対応策も講じられています。
競争優位性の評価
ウェブ検索では、マンション建設に強みがあるという情報以外に、明確な競争優位性を示す詳細な情報は見つかりませんでした。他社と差別化できる技術力やブランド力、顧客基盤といった具体的な競争源泉については、より詳細な分析が必要です。
最近の動向
- 2026年3月期第1四半期決算で経常利益が大幅に増加しました。
- 増配が発表され、株主還元への積極的な姿勢が示されました。
- 投資ファンドによる株式の買い増しが明らかになり、市場からの注目度が高まっています。
総合評価と投資判断
大末建設は、建設業という事業の性質上、ディフェンシブコアの投資スタイルに適した特性を持っています。直近の業績や積極的な株主還元方針は魅力的です。しかし、中長期的な成長の不確実性が払拭できないため、組み入れを検討する価値はあるものの、他に上位評価の銘柄がない場合の選択肢の一つと位置付けるのが妥当でしょう。
AI評価(結論)
★★★☆☆
管理人考察
AI分析の補足しておきたいポイント
AI分析では「マンション建設に強みがある」という一般的な情報に留まった為、
技術、ブランド力、顧客基盤といった具体的な競争源泉が、
どのように他社との差別化につながっているかという深い分析が必要です。
高い利益率や再現性を裏付ける具体的な指標に関する情報も不足しており、
ビジネスモデルのスケーラビリティや効率性も補完したいところです。
総合評価
管理人注目度:★★★☆☆
今年に入って新興運用会社のfundnote(井村ファンド)の大量保有が発覚したことで、
注目を集めている企業です。
ファンド自体の注目度が高い為か、大末建設の株価は上昇トレンドを形成していますが、
彼らが何を評価・期待してこの銘柄を保有したか、今後も堅調な株価の推移が見込めるかなど、
自身の判断軸を持って評価することが求められます。
“目的を「重要提案行為を行う」に変更する場合がある”と明言されているのも気になる点で、
ファンドの動向まで予測した上で投資を検討すべきでしょう。
ファンドの動向を抜きにすると、可もなく不可もなくといった銘柄に見えます。
配当利回りが良い、割安感ありといった要素はありますが、
売上は拡大中だが収益力に課題、規模は小さめでディフェンシブ性が限定的など、
より有力な候補を探したい要素もあります。
ぱっと見は特筆すべき強みは見出しにくいですが、深掘りの優先度は高くできそうな、
特殊な立ち位置の銘柄です。
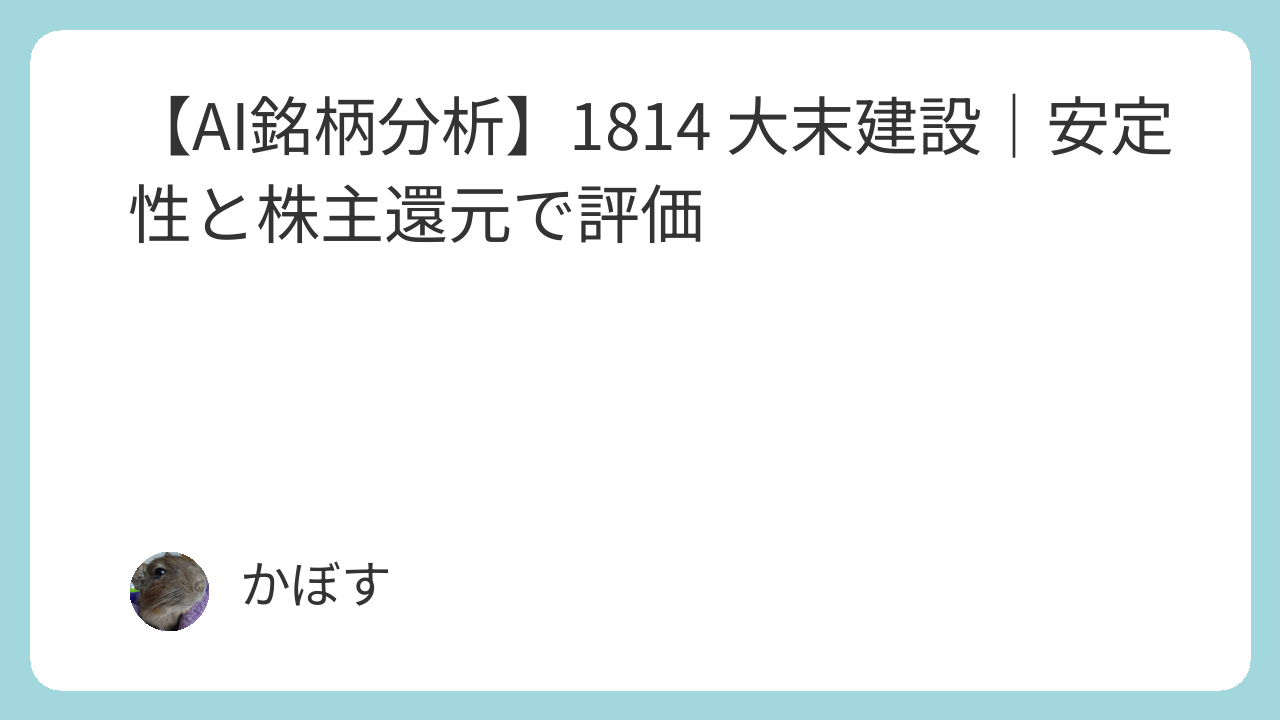
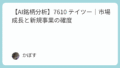
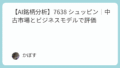
コメント