📊 この銘柄分析は、AIによる自動分析と公開評価基準に基づいて作成しています。
➡️ AIの銘柄評価基準はこちら
🤖 使用AIの情報はこちら
企業紹介
オープンアップグループ(2154)は、技術者派遣を主軸とする企業です。特にITインフラ、機械設計・電気、建設分野において、未経験者を独自のプログラムで育成し、即戦力として市場に供給する「人材成長支援事業」を核としています。これは、社会的な技術者不足という構造的な課題解決に貢献するビジネスモデルであり、同社の強固な競争優位性の源泉となっています。
AI銘柄分析レポート
はじめに
この記事では、オープンアップグループ(2154)について、AIによる多角的な視点からその投資魅力を分析します。具体的には、収益性、成長性、財務健全性、株価水準、および競争優位性といった主要な評価軸に基づき、本銘柄がキャピタルゲイン狙いの投資候補としてどの程度の魅力を持つのかを検証します。
収益性の評価
同社の収益構造は、技術者派遣というストック型ビジネスモデルにより極めて高い安定性を有しています。単価の高い技術者を継続的に提供することで、売上高が着実に積み上がる構造です。
- 営業利益率: 2026年6月期には9.6%を目指す計画であり、利益率は改善傾向で推移しています。これは、単に人材を派遣するだけでなく、未経験者を独自のノウハウで育成し市場価値を高めるという高付加価値モデルが奏功しているためです。
- 収益性の持続可能性: 少ない追加投資で新たな技術者を生み出すというスケーラビリティと再現性の高いモデルを確立しており、高い資本効率(ROE 16.52%)を維持しています。
成長性の評価
オープンアップグループの成長ドライバーは、極めて確度が高いと評価されます。日本のDX化と労働人口減少に伴う技術者不足は構造的な問題であり、同社の主要市場は今後も需要が持続的に拡大することが見込まれます。
- 成長目標: 国内エンジニア数を年率10%以上増加させることを目標としています。
- 成長の裏付け: 成長の根幹は「年間1,500名超」の未経験者採用と、その後の「独自の育成ノウハウ」であり、これは景気に左右されにくい内製化された成長システムです。
- M&A戦略: 育成ポートフォリオや成長分野を強化するためのM&Aを継続的に検討しており、これがさらなる成長加速の余地を提供しています。
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 最終利益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) |
| 2022.06 | 148,573 | 10,103 | 10,238 | 6,975 | 78.3 | 45 |
| 2023.06 | 150,697 | 12,164 | 12,508 | 9,533 | 109.1 | 50 |
| 2024.06 | 173,225 | 14,293 | 14,555 | 11,768 | 135.8 | 65 |
| 2025.06 予 | 187,954 | 16,244 | 16,172 | 12,559 | 144.6 | 75 |
| 2026.06 予 | 171,000 | 16,500 | 16,500 | 11,800 | 139.0 | 85 |
財務健全性の評価
同社の財務状況は非常に盤石であり、安全性が高いと評価できます。
- 安全性指標: 自己資本比率は64.2%(実績)と高水準であり、流動比率も200%を超えていると推定されます。
- キャッシュフロー: 安定したストック型収益構造により潤沢なキャッシュフローを有しており、成長投資や株主還元を支える強固な基盤となっています。
割安性・株価水準の評価
(2025年11月時点の株価1,767円、2026年6月期会社予想ベース)
- PER: 12.87倍。年率10%以上の成長目標を持つ企業、かつグローバル競合(例:Adecco 15.5倍)と比較しても割安な水準にあります。
- PBR: 2.04倍(実績)。PBRはグローバル競合と比較して割高に見えますが、これはROEが16.52%という高い資本効率を維持していることの裏返しと解釈できます。
- 配当利回り: 4.8%(予想)。配当性向50%以上、累進配当を掲げており、キャピタルゲイン狙いだけでなく、インカムゲインの観点からも優良な水準です。
現在の株価水準は、成長性と安定性を鑑みると過小評価の傾向にあると評価できます。
事業リスクと対応策
投資家として注目すべき主要なリスク要因は以下の3点です。
- 人材の定着率(LTVの維持): 育成した優秀な人材の離職が増加すると、収益性に直接悪影響を及ぼします。同社はキャリアサポートや継続的な育成投資により定着率の維持に努めていますが、稼働率や離職率の推移を注視する必要があります。
- 中期経営計画の利益率目標(9.6%)の達成状況: 単価上昇とコスト効率化の進捗を示す重要な指標であり、四半期ごとの推移を継続的に確認すべきです。
- M&Aの質の維持とPMI (統合) リスク: 成長を加速させるためのM&A戦略において、シナジー効果の低い買収やPMIの失敗はリスクとなり得ます。
競争優位性の評価
同社の最も強固な競争優位性(Moat)は、**「未経験者を体系的に技術者に育成する内製化された人材成長支援モデル」**です。
- 独自のサプライチェーン: 採用ターゲットを「未経験者」に特化することで、競合との人材獲得競争を避け、年間1,500名超という圧倒的な採用・育成キャパシティを確立しています。
- 参入障壁: この体系的かつ継続的な育成プロセスは、短期間で他社が追随することが困難な構造的な参入障壁となっており、これが安定的な成長の源泉となっています。
- 防御策: 高い配当性向による資本政策と社員への継続的な育成投資が、優秀な人材の獲得と定着に繋がり、Moatをさらに強化する好循環を生み出しています。
最近の動向
直近1年間、同社の株価は堅調に推移しています。その主な背景として以下の要因が挙げられます。
- 好決算の継続: 四半期決算において継続的な増収増益を達成しており、中期経営計画の現実性が市場で再評価されています。
- 積極的な株主還元: 自社株買いの実施や、配当性向50%以上というコミットメントがPBR是正期待を高めています。
- 高付加価値化の進捗: IT部門における契約単価の継続的な上昇など、育成モデルの収益化が具体的に進んでいることが確認されています。
総合評価と投資判断
オープンアップグループは、構造的な人材不足という社会課題を解決しながら成長する、再現性の高いビジネスモデルを確立しています。この堅実な成長ポテンシャルに対してPERが割安水準にあり、キャピタルゲイン狙いの候補として組み入れを検討する価値がある銘柄です。
ただし、キャピタルゲイン狙いの銘柄のなかでも、特に高い成長性(例:年平均30%以上の利益成長が複数年にわたり確実視される)を要求する厳格な基準には、現時点の成長率目標(エンジニア数年率10%増)では合致しません。そのため、余力と、他の保有銘柄とのリターン、リスク、Moatの比較検討が重要になります。
AI評価(結論)
★★★★☆
- 評価理由: 高い成長ポテンシャルと明確な成長ドライバー、そして星5つに匹敵する強固な競争優位性(Moat)を持ちます。現在の株価も魅力的であり、リスクを考慮しても十分なリターンが期待できる、ポートフォリオの核となりうる有力な候補です。
管理人考察
AI分析の補足しておきたいポイント
- 育成後の人材の具体的な離職率(定着率)の推移:
LTV(生涯価値)の計算と、ビジネスモデルの持続性を評価する上で最も重要な指標です。IR資料などで具体的な数値が開示されていれば、成長の質の確実性をより厳密に評価できます。 - 教育研修コンテンツ(IP)への投資額とM&A後のPMIの具体的内容:
競争優位性の維持・強化に不可欠な育成プログラムへの具体的な投資額、およびM&A後の事業統合がどのように成功しているか(例:売上・利益への貢献度)を深掘りすることで、経営計画の実行力をより正確に評価できます。
総合評価
管理人注目度:★★★★☆
未経験者を体系的な教育により技術者に育成するノウハウが特徴で、
これは持続的な成長性と競争優位性の源泉として同業他社と差別化できる要素です。
安定的な規模の拡大が可能なモデル、財務は安定しており配当利回りも高く、
株価指標に過度な割高感もなく、市場から再評価される余地はあると思います。
ただし、これらは育成した人材が競合に引き抜かれず、自社に定着することが前提です。
また、堅実ではあるものの高成長とはみなしにくい業績推移で、
成熟企業として評価するなら現在の株価指標は妥当である可能性もあります。
ポテンシャルを秘めた企業として市場評価とのギャップを見出すためには、
人材の単価向上と流出リスクという相反しやすい課題とどう向き合うか、
質を伴ったM&Aが実行できるか、といった点を注意深く見る必要がありそうです。
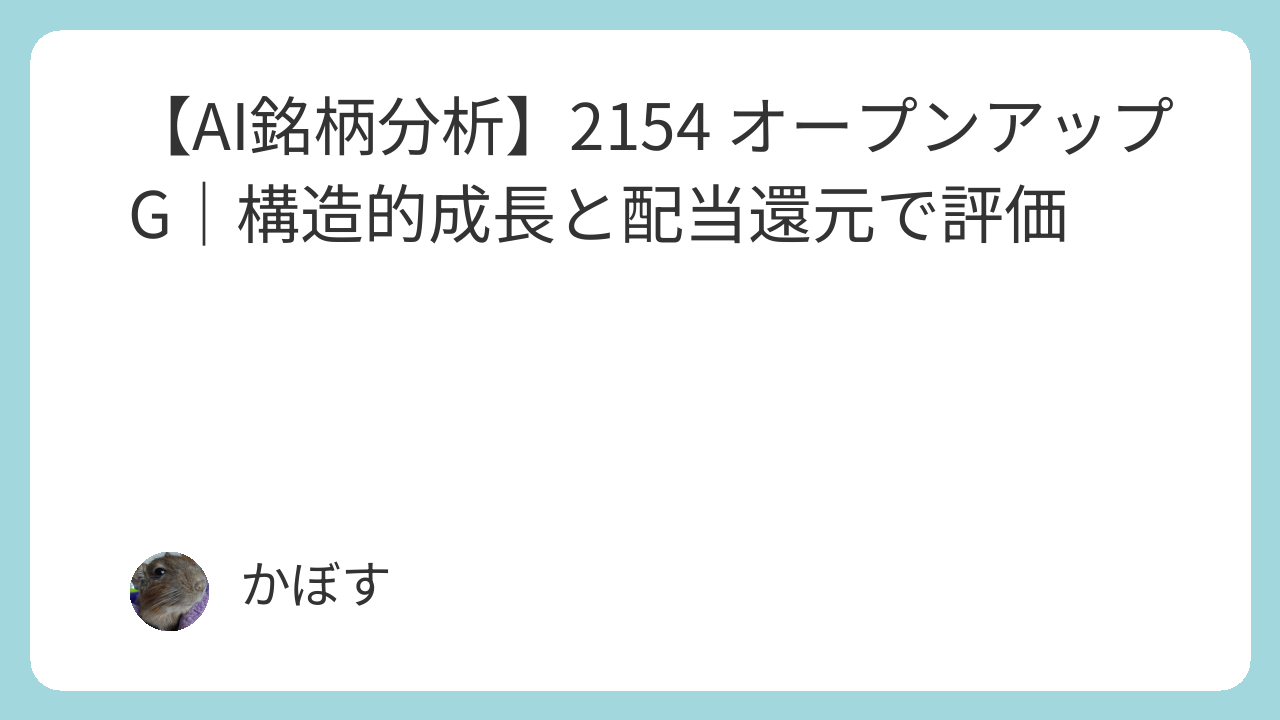
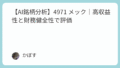
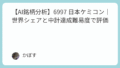
コメント